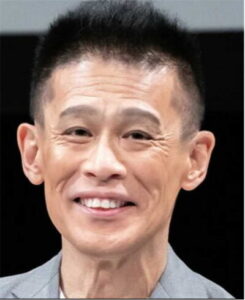2025年10月6日、大阪大学の坂口志文特任教授がノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
受賞理由は「制御性T細胞」の発見です。
この細胞は、がん治療や難病治療に革命をもたらす可能性を秘めています。
しかし「制御性T細胞って何?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、医学知識がない方でもわかるように、制御性T細胞を徹底解説します。

制御性T細胞とは「免疫のブレーキ役」
制御性T細胞を一言で表すと「免疫のブレーキ役」です。
私たちの体には、細菌やウイルスと戦う免疫システムがあります。
この免疫は通常、外敵だけを攻撃します。
しかし、時に暴走して自分の体まで攻撃してしまうことがあるのです。
例えば、車にはアクセルとブレーキがありますよね。
免疫細胞がアクセルだとすれば、制御性T細胞はブレーキにあたります。
適切なタイミングでブレーキをかけることで、免疫の暴走を防ぐのです。
制御性T細胞は、体内の免疫細胞全体のわずか約10%しか存在しません。
しかし、この少数精鋭の細胞が、免疫システム全体のバランスを保っているのです。
坂口氏は1995年、この細胞の目印となる「CD25」という分子を発見しました。
なぜ医療にとって重要なのか
制御性T細胞の発見は、多くの病気の治療に道を開きました。
最も期待されるのが、自己免疫疾患の治療です。
関節リウマチや1型糖尿病は、免疫が自分の体を攻撃してしまう病気です。制御性T細胞を増やすことで、この攻撃を抑えられる可能性があります。
がん治療への応用も注目されています。がん細胞の周囲には制御性T細胞が集まり、がんへの攻撃を妨げています。
この細胞を一時的に減らせば、免疫ががん細胞を攻撃しやすくなるのです。
さらに、臓器移植の拒絶反応を抑える効果も期待されています。
従来の免疫抑制剤は全身の免疫を弱めますが、制御性T細胞なら移植臓器への攻撃だけを抑えられる可能性があります。
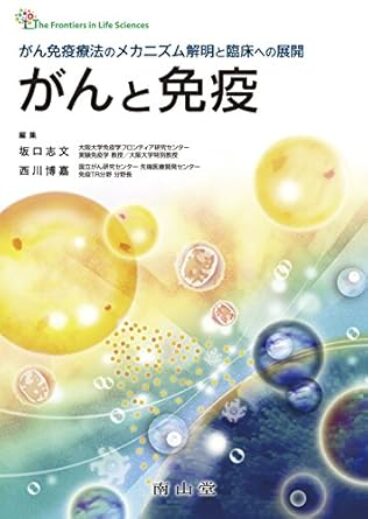
📚 さらに専門的に学びたい方へ~
ノーベル賞受賞者・坂口志文氏が編集した専門書『がんと免疫』。
制御性T細胞とがんの関係、最新の免疫療法まで、
第一線の研究者たちが基礎から臨床応用まで徹底解説。
がん免疫研究の現在と未来がわかる決定版です。
20年の苦労を経た大発見
坂口氏の研究は、決して順風満帆ではありませんでした。
1995年に制御性T細胞の存在を発表した時、多くの研究者は信じませんでした。
「免疫を抑える細胞があるはずがない」という常識に反していたからです。
しかし坂口氏は確信を持っていました。
地道に実験を重ね、20年近くかけて自説の正しさを証明したのです。
2000年に「制御性T細胞」と正式に命名され、ようやく世界に認められました。
実用化への期待高まる
現在、制御性T細胞を使った治療法の研究が世界中で進んでいます。
2022年からはがん治療の臨床試験も始まっています。
患者の血液から細胞を取り出し、体外で制御性T細胞を増やして戻す方法が開発されています。
坂口氏のノーベル賞受賞により、制御性T細胞研究はさらに加速するでしょう。
「免疫のブレーキ役」が、難病に苦しむ多くの患者を救う日も遠くありません。
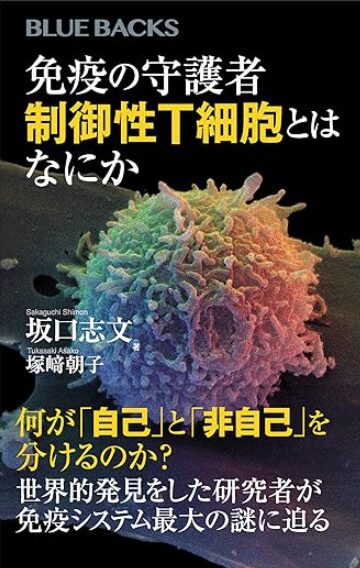
📚さらに詳しく学びたい方へ ノーベル賞受賞者・坂口志文氏ご本人が書かれた一般向け書籍がおすすめです。 **『免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか』(ブルーバックス)** この記事では基本だけをご紹介しましたが、坂口氏の研究の全貌や20年の苦労、 医療への応用可能性をさらに深く知りたい方は、ぜひご一読ください。